第1回:【保存版】初心者でも迷わない!コード進行テンプレート10選【作曲にすぐ使える】
「メロディは浮かんだけど、コードがわからない…」
「コード進行ってどう選べばいいの?」
そんな悩みを持つ初心者の方へ。
コード進行は、曲の “骨格” とも言える大切な要素。
感情や雰囲気を決める鍵でもあります。
このシリーズでは、初心者が迷わず使えるコード進行をテーマに、
作曲のステップを丁寧に解説していきます。
コード進行シリーズ一覧(全5回予定)
- 第1回:初心者でも迷わない!コード進行テンプレート10選 ← 今回の記事
- 第2回:Aメロ・Bメロ・サビで使えるコード進行ガイド
- 第3回:コード進行からメロディを作る!初心者向けステップ講座
- 第4回:コード進行が浮かばない時の“ひらめきリスト”
- 第5回:同じキーでも雰囲気が変わる!ダイアトニックコードの使い分け
今回は第1回として、すぐに使えるコード進行テンプレートを10個紹介します。
すべてダイアトニックコード中心なので、理論がわからなくても安心。
曲の雰囲気に合わせて選べるようにしています!
ダイアトニックコードって何?
まずは簡単におさらい。
ダイアトニックコードとは、あるキーのスケール内で自然にできるコードのこと。
たとえば、Cメジャーキーなら以下の7つ:
| コード | 役割 | 雰囲気 |
|---|---|---|
| C(I)トニック | 安定 | 明るく落ち着く |
| Dm(II)サブドミナント | 補助 | 優しくつなぐ |
| Em(III)トニック | 軽さ | 少し切ない |
| F(IV)サブドミナント | 展開 | 前向きな広がり |
| G(V)ドミナント | 緊張 | 次に進みたくなる |
| Am(VI)トニック | 感情 | 切ない、力強い |
| Bdim(VII)ドミナント | 不安定 | 夢の中のような揺らぎ |
※IIIコードは完全なトニックではなく、トニック寄りの中間的な響きを持つコードです。
切なさや軽さを加える役割としてよく使われます。
より詳しい内容を知りたい方はこちらの記事を確認ください。
👉【作曲初心者必見】Cコードから広がるダイアトニックコードの世界|曲作りが驚くほどスムーズになる理由
コード進行テンプレート10選(Cメジャーキー)

それぞれの進行、使いやすい場面、コード譜例を添えて紹介します。
1.王道進行(I – VI– IV– V)
コード例:C – Am – F – G
コードの役割:トニック – トニック – サブドミナント – ドミナント
明るい・ポップ・親しみやすい
ポップスで最もよく使われる進行。サビやループに最適。
ポップスの定番中の定番。安定感があり、どんなメロディにも合わせやすい進行です。
ポイント:I(C)から始まり、VI(Am)で少し感情を入れ、IV(F)で広がり、V(G)で次への期待を作る流れ。
初心者向けヒント💡
この進行はループしやすいので、Aメロやサビに繰り返して使うと自然な構成になります。
2. 小室進行(VI–V–IV–V)
コード例:Am – G – F – G
コードの役割:トニック – ドミナント – サブドミナント– ドミナント
切ない・懐かしい・90年代風
この進行は、日本の音楽シーンで小室哲哉さんが多用したことから「小室進行」と呼ばれるようになりました。
正式な音楽理論用語ではなく俗称ですが、J-POPでよく使われる進行として広く浸透しています。
Amから始まることで、切なさと爽やかさが同居した力強いコード進行
ポイント:感情的な入り口(Am)から、徐々に明るさへと展開していく構造。
応用:テンポを落とすとバラード風に、速くすると懐かしいダンス系にもなります。
3.カノン進行(I–V–VI–III–IV–I–IV–V)
コード例:C – G – Am – Em – F – C – F – G
コードの役割:トニック – ドミナント – トニック– トニック
– サブドミナント – トニック – サブドミナント – ドミナント
壮大・クラシカル・感動的
クラシックの「パッヘルベルのカノン」に由来する進行。
長めの構成で、物語性があります。
ポイント:コードが滑らかに動き、メロディが乗せやすい。
初心者向けヒント:コード数が多いので、まずは前半4つだけ使ってみるのもOK!
イントロやエンディングに使うと印象的。
4. 4536 進行(IV–V–III–VI)
コード例:F – G – Em – Am
コードの役割:サブドミナント – ドミナント – トニック – トニック
落ち着き・大人っぽい・ジャジー
Bメロや間奏に使うと雰囲気が変わります。
コードの流れが滑らかで、メロウな雰囲気を演出できます。
また、サビなどでも使うことができる進行です。
ポイント:IV→Vで展開し、III → VIでしっとりと落ち着く流れ。
応用:テンションコード(Fmaj7 や Em7)を使うと、さらに深みが出ます。
5. 3625 進行(III–VI–II–V)
コード例:Em–Am–Dm–G
しっとり・夜・ジャズ風
ジャズの定番「循環コード」に近い進行。
コードが順に下がっていくことで、落ち着いた印象になります。
ポイント:Em→Am→Dm→Gと、自然な流れで次に進む構造。
初心者向けヒント:メロディはコードトーン中心にすると、安定感が出ます。
ジャズの定番進行。
静かなイントロやAメロ、落ち着いたサビにぴったりです。
6. 6245 進行(VI–II–IV–V)
コード例:Am–Dm–F–G
切ない・前向き・感情の流れ
一般的に定着した名前はありませんが、
Amから始まることで、少し切ない雰囲気を持ちながら、
Dm→F→Gと進むにつれて徐々に前向きな展開へと移っていきます。
この進行は、感情のグラデーションを描きたいときにぴったり。
Aメロで静かに始まり、Bメロでこちらの進行を使い、サビに向けて気持ちを高めるような構成に向いています。
ギターでも弾きやすく、コードチェンジが自然なので、弾き語りやループにも適しています。
メロディはAmやDmのコードトーンから始めると、流れがスムーズになります。
7. 1564 進行(I–V–VI–IV)
コード例:C–G–Am–F
感動・希望・エモーショナル
洋楽で非常によく使われる進行で、海外では「Axis of Awesome進行」として知られています。サビで感情を爆発させたいときにぴったりです。
C → G で期待を高め、Am → Fで感情を広げる流れが
ドラマチックな印象を与えます。
メロディに跳躍を入れるとよりエモーショナルになり、
感動的な展開を作りたいときにおすすめです。
8. 1625 進行(I–VI–II–V)
コード例:C–Am–Dm–G
切なさ・余韻
流れがスムーズで、メロディが乗せやすい進行です。
C→Am→Dm→Gと、自然な展開で次に進みやすく、安定感があります。
この進行をループさせるだけで、1曲の骨格が作れるほど汎用性が高いです。
9. 1646 進行(I–VI–IV–VI)
コード例:C–Am–F–Am
切ない・揺らぎ・余韻
一般的に固有名はありませんが、Amが繰り返し登場することで余韻が残り、切ない雰囲気を作る進行です。
感情の揺らぎや静かな場面にぴったりで、エンディングや落ち着いたパートに使うと効果的です。 Amのコードトーンを中心にメロディを作ると、まとまりが出て雰囲気が安定します。
10. 1456 進行(I–IV–V–VI)
コード例:C–F–G–Am
希望・展開・少し切ない
固有名は特にありませんが、C→F→Gで展開し、Amで感情を加える万能型の進行です。
明るさの中に少し感情が混ざる進行です。
サビの後半や転調前のつなぎに使うと、感情の深みが増して印象的な展開になります。
ポップスからバラードまで幅広く使える万能型です。
実際に使ってみよう!

ギターでコードを弾いてみたり、DAWやDTMソフトで、
上記のコード進行を打ち込んでみましょう。
それぞれのコード進行の中で自分好みのものがありましたら、そこから作曲に取り組んでみるもの良いでしょう。
また、コード譜だけでなく、コードトーン(ルート・3度・5度)を意識してメロディを作ると、より自然な曲になります。
関連リンク
まとめ:コード進行は“感情の地図”

コード進行を知ることで、曲作りはぐっと自由になります。
今回紹介したコード進行を使えば、初心者でもすぐに曲の骨格を作ることができます。
ぜひ、自分の感情に合った進行を選んで、まずは鼻歌からメロディを乗せてみてくださいね!

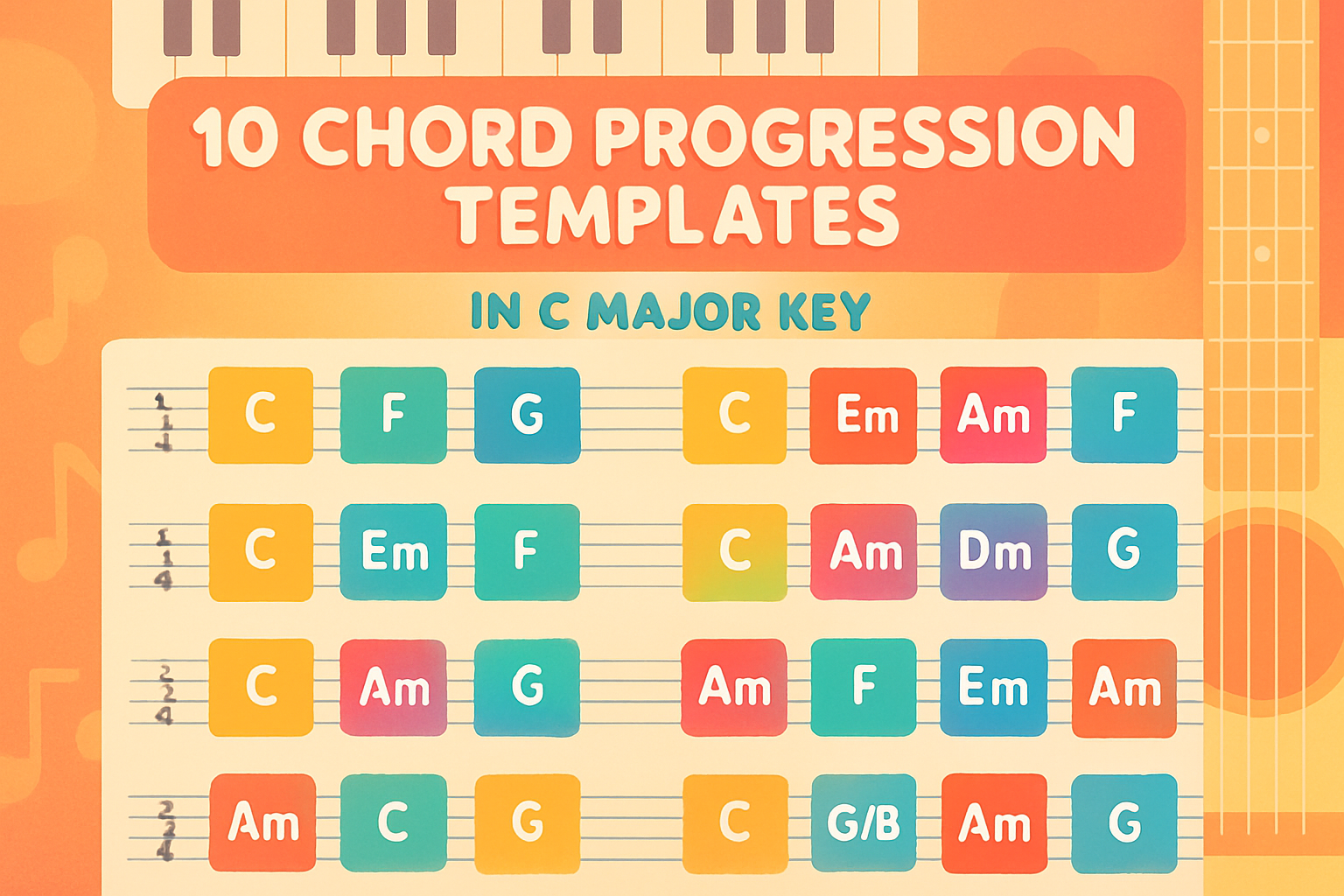

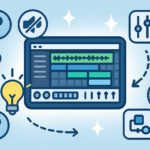
コメント