第4回|モニターヘッドホンの選び方:DTM初心者から中級者まで納得の一台を見つけよう!
DTM(デスクトップミュージック)を始めたばかりの方にとって、
「モニターヘッドホン選び」は意外と難しい壁かもしれません。
「普段使っているヘッドフォンと何が違うの?」
「どれも似たように見える…」「高いモデルを買えば間違いない?」
そんな疑問に、今回はやさしく解説します。
最後まで是非ご覧ください!
👉 本記事は「DTM初心者シリーズ」の第4回です。
-
- 第1回:【超入門】DTMに必要な最低限の機材・ソフトまとめ
- 第2回:【DAWってなに?】初心者におすすめのDAW 5選 比較ガイド
- 第3回:【DTM初心者あるある】最初につまずくポイントと解決策
- 第4回:モニターヘッドホン選び方 ← 今回の記事
モニターヘッドホンとは?リスニング用との違い

モニターヘッドホンは、音楽制作や録音の現場で使われる
「原音に忠実な音」を再現するためのヘッドホンです。
リスニング用との違いは、音の加工がほとんどされていないこと。
低音や高音を派手に強調せず、音楽を「楽しむ」ためではなく
「正確に聴く」ための道具です。
そのため、リスニング用で「迫力がない」と感じても、制作ではむしろ正確さが重要になります。
モニターヘッドホンの選び方:5つのポイント
1. 密閉型 or 開放型?
- 密閉型:外部の音を遮断し、音漏れも少ない。
レコーディングや外出先での作業に向いている。 - 開放型:自然な音の広がりが魅力。
耳が疲れにくく、ミックス、マスタリングや長時間作業におすすめ。
2. 解像度の高さ
音の輪郭がはっきりしているほど、細かなニュアンスまで聴き取れます。
特にボーカルのブレスやリバーブのかかり具合など、
繊細な部分を判断する際に解像度の高さが役立ちます。
3. 装着感
長時間の作業では、耳や頭への負担が大きくなります。
軽量でイヤーパッドが柔らかいモデルや、
ヘッドバンドが広めで圧迫感が少ないものを選ぶと快適です。
また重量感も個人差があるので意識してみると良いと思います。
4.リケーブル対応
ケーブルは断線しやすい消耗品。交換可能な「リケーブル対応モデル」なら長く使えて経済的です。
ストレートケーブル・カールケーブルなど作業環境に合わせて選べるのもメリットです。
5. 用途に合わせた選択
- DTM・ミックス作業:開放型+高解像度
- レコーディング:密閉型+遮音性
- 外出先や移動中:軽量・密閉型・オンイヤータイプ
一台ですべてをカバーするのは難しいため、制作とリスニングで使い分けるクリエイターも少なくありません。
おすすめモニターヘッドホン

1. SONY MDR-M1ST(密閉型)
-
- 再生周波数帯域:5Hz〜80kHz
- 重量:約215g
- 特徴:ソニーとソニーミュージックが共同開発。
- ハイレゾ対応、快適な装着感、国内スタジオ標準の新定番モデル
▶Amazon / SONY/MDR-M1ST
2. Audio-Technica ATH-R70x(開放型)
- 再生周波数帯域:5Hz〜40kHz
- 重量:約210g
- 特徴:オーディオテクニカ初のフラッグシップ開放型モニターヘッドホン。自然な音場と軽量設計でミックス作業に最適
▶Amazon / Audio-Technica ATH-R70x
3. AIAIAI TMA-2 Studio Wireless+(密閉型・ワイヤレス)
- 再生周波数帯域:10Hz〜40kHz
- 重量:約270g
- 特徴:低遅延ワイヤレス伝送(W+ Link)、有線接続も可能。
モジュール交換式でカスタマイズ性が高く、サステナブル設計
▶Amazon / Audio-Technica ATH-R70x
選び方のコツ:試聴と比較が大切
スペック表やレビューだけでは、実際の音の印象や装着感までは分かりません。
可能であれば楽器店やオーディオショップで試聴し、複数モデルを比較するのがおすすめです。
「低音の出方」「音場の広さ」「自分の声や楽器がどう聴こえるか」をチェックすると、制作に合うモデルを見つけやすくなります。
初心者がやりがちな失敗と価格帯の目安
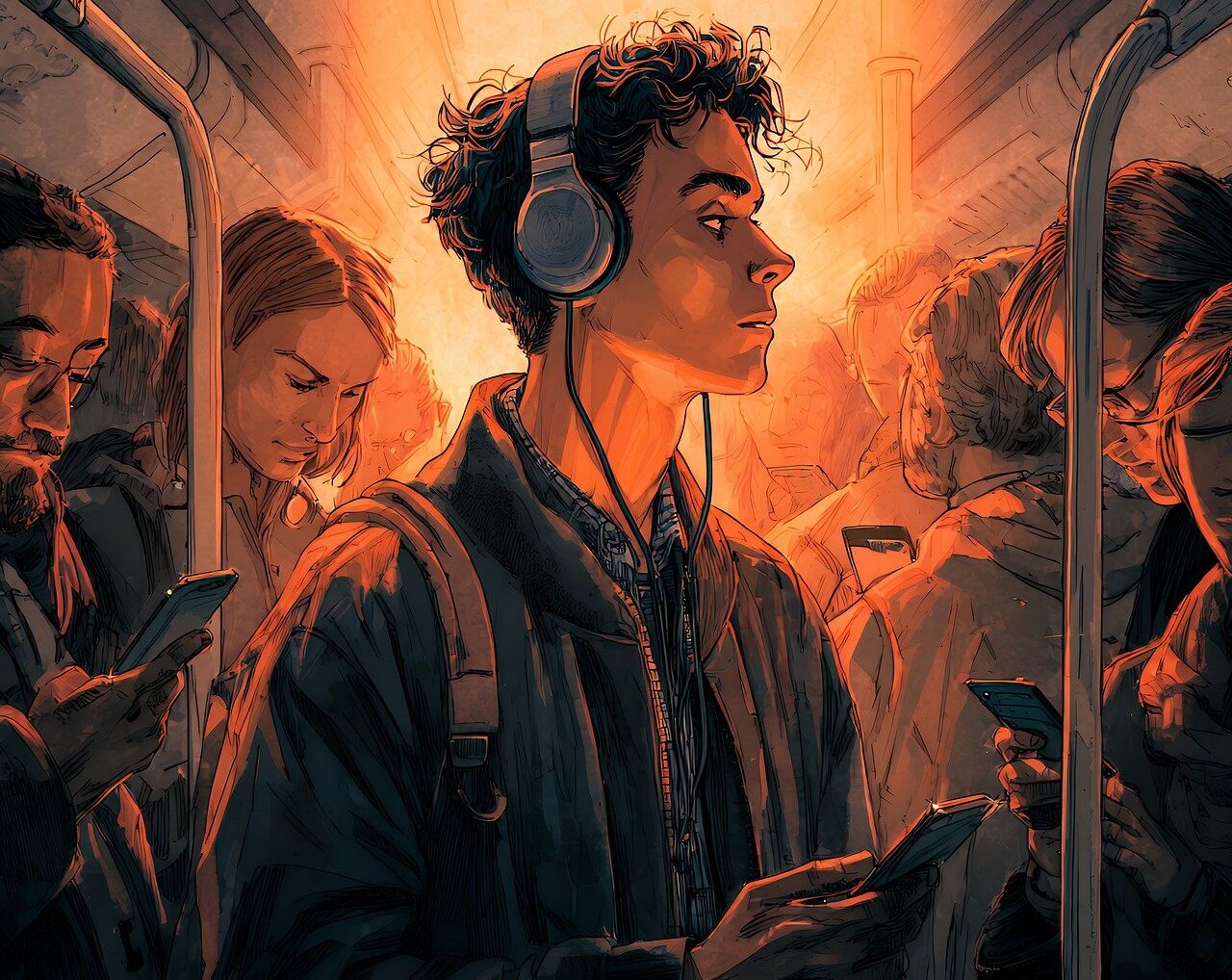
DTM初心者の方によくある失敗は
「安価なリスニング用ヘッドホンで代用してしまう」ことです。
低音が強調されすぎていたり、高音が派手に聞こえたりするため、
ミックスを仕上げても他の環境で聴くとバランスが崩れてしまうことがあります。
モニターヘッドホンは 5,000 円程度の入門モデルから
数十万円クラスのハイエンドまで幅広いですが、
最初の一台としては1万〜2万円台のモデルがコストパフォーマンスに優れおすすめです。
この価格帯なら解像度も十分で、
DTMを続けていく中で「次に必要な性能」が見えてくるため、
将来的な買い替えにも無駄になりません。
まとめ:自分の制作スタイルに合った一台を

モニターヘッドホンは、音楽制作の「耳」となる大切な道具。
価格やブランドだけで選ぶのではなく、
自分の制作スタイルや環境に合わせて選ぶことが、長く快適に使うコツです。
「迷ったら密閉型を最初の一台にし、必要に応じて開放型を追加する」
という選び方もおすすめです。
関連記事リンク




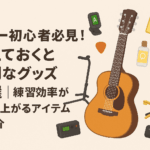

コメント